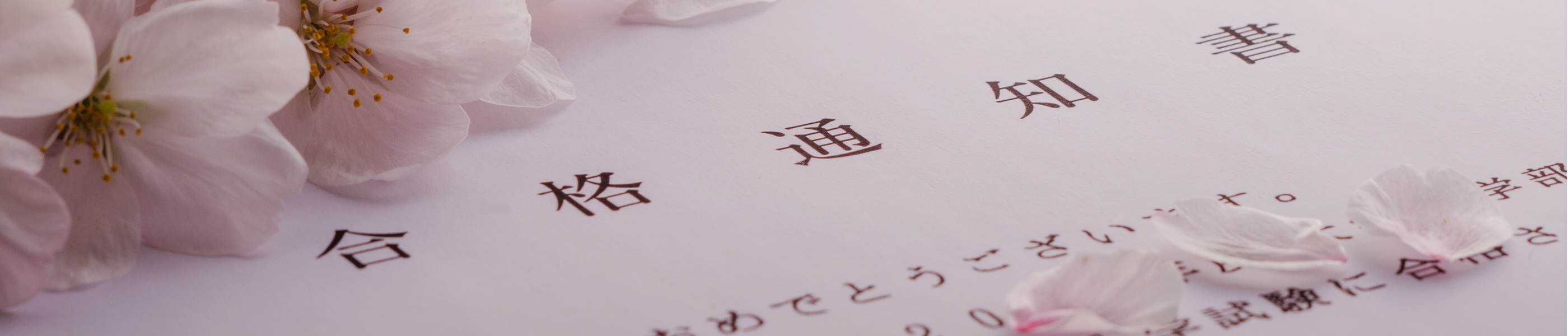Blog コラム
実は東京都内ではコスパ最強!?高大一貫校の高校入試とは?そのメリットとデメリットを紹介

文京区の個別指導塾 ESCAの岸田です。
本記事では、東京都内に在住の中高生の保護者の方々に向けて、「高大一貫校の高校入試」について詳しく解説します。
学習塾ESCAには中学受験を経験した講師も在籍していますが、実は塾長である岸田自身は高校受験組で、成績が一番伸びたのも高校受験の時でした。
そんな私が、実は東京都内では公立中+学習塾で高大一貫校受験こそがコスパ最強!と感じる理由を書いていきたいと思います。
近年、首都圏では中学受験が非常に盛り上がっており、私立や国立附属の中高一貫校への進学を検討するご家庭も増えています。しかし、「中学受験」は小学生の段階で始まるため、受験準備のスケジュールが早まり、学習費用も高額になるという側面があります。
そこで注目されているのが「高大一貫校の高校入試」という選択肢です。大学までエスカレーター式で進学できる利点や、一般的な高校と比較したときのメリット・デメリット、さらに中学受験と比べた際のコスト面での利点などを中心にご紹介します。
本記事は以下の構成でまとめています。
1. 都内の中学受験率
2. 中学入試の偏差値と高校入試の偏差値の違い
3. 高校入試で受験できる関東圏高大一貫校の例
4. 高大一貫校のメリット
5. 高大一貫校のデメリット
6. 中学受験と比較した際の高大一貫校のコストメリット
7. まとめ
それでは順番に見ていきましょう。
1. 都内の中学受験率
中学受験率の概況
東京都内では、中学受験を選択する小学生の割合が全国平均よりも高いことで知られています。一般的には全国的に見ると中学受験率は10〜15%前後とも言われますが、首都圏(特に東京23区)に限っては25〜30%あるいはそれ以上になる地域も存在します。学習意欲の高い家庭が多いこと、私立中高一貫校が豊富にあることなどが理由として挙げられます。
背景にある「将来への備え」
なぜ首都圏でこれほど中学受験が盛んなのか。大きな理由の一つとして、大学受験対策をできるだけ早期にスタートさせたいという保護者のニーズがあります。大学進学がほぼ前提となる社会状況のなかで、難関大学に合格するためには中学・高校の段階で適切な受験対策が必要だと考えるご家庭が増えているのです。
一方で中学受験は小学校4年生頃から本格的な塾通いを開始するどころか、年々塾通いの早期化が目立ちます。親子ともに負担が大きいのも事実です。結果として、中学受験を終えた頃に燃え尽き症候群のようになってしまう子どもも一定数いるというデメリットも指摘されています。
2. 中学入試の偏差値と高校入試の偏差値の違い
偏差値の算出母集団が異なる
「偏差値」という言葉は、受験の難易度を測る大まかな指標として広く使われています。しかし、中学入試と高校入試の偏差値は、単純に比較することができません。その大きな理由は“算出母集団の違い”にあります。
• 中学入試の偏差値:全国または首都圏レベルの中学受験塾に通う、比較的学力の高い(あるいは学習意欲の強い)集団が母集団になることが多い。
• 高校入試の偏差値:公立・私立を問わずに受験を検討する生徒が幅広く存在するため、母集団が中学入試よりも大きく、学力分布も多様になる。
こうした背景があるため、たとえば中学入試偏差値「50」が高校入試偏差値「60」に相当するといったように、単純な比較はできません。加えて、受験形式や試験科目の違いなどもあるため、「中学受験と高校受験の偏差値は別物」と考えたほうがよいでしょう。
学力到達度の違い
中学受験の偏差値が高い学校は、単に問題の難易度が高いだけでなく、出題範囲が小学校の内容を超えた発展的な問題が含まれることも多いです。
一方で高校受験の場合は、中学校で習う内容が範囲となり、文部科学省の定める学習指導要領に準拠することが基本です。したがって、問題の出題傾向や難易度、必要な思考力に違いが出てくるのは当然といえます。
首都圏では高校受験の方が楽な場合がある
都内の中学受験率、偏差値や入試作成の背景から、実は公立中学校+塾で高校受験の方が楽な場合もあります。その理由を見ていきましょう。
※以下は全て「中学受験に比べて」という意味です。
①アッパー層が中学受験でいなくなる
中学入試でアッパー層の多くは中高一貫校に進学するため、高校受験の母集団としてはアッパー層が少なくなります。また、競争相手のほとんどは公立中学校に通っており、学習塾に通っていなければ進度が非常にゆっくりなので、演習量に差ができます。
②範囲が少なく問題パターンも限られている
問題パターンが限られているというよりも、アプローチの方法が限られていると行った方が良いかもしれません。よって、逆転合格を狙いやすいのです。
③システマティックな対策が可能で地頭の良さに左右されにくい
②と似ていますが、パターンが限られているため、対策が非常にしやすいです。努力がそのまま結果につながると言った方が良いかもしれません。努力がなかなか報われない、と言われる生徒でも、高校受験にならチャンスがあります。
3. 高校入試で受験できる関東圏高大一貫校の例
高大一貫校とは
「高大一貫校」とは、高校と大学が連携しており、内部進学で大学までエスカレーター式に進める仕組みがある学校を指します。厳密な定義はやや曖昧ですが、一般的には大学の附属・系属高校がこれに当たります。代表的な例として、早稲田大学系属校、慶應義塾大学の附属校、上智大学の附属校、立教大学の附属校、明治大学・青山学院大学・中央大学・法政大学などの付属校もあります。
ただし、すべての附属校が中高一貫(中学受験のみ)かというとそうではなく、高校からの募集枠がある学校も多数存在します。首都圏では中学からしか入学できない学校もありますが、一定数の募集枠を高校入試で設けている大学附属校があります。
関東圏で高校入試を実施している主な大学附属校(一例)
• 早稲田大学系属:早稲田実業学校高等部(中学からの募集がメインだが、高校募集もあり)
• 慶應義塾:慶應義塾志木高等学校、慶應義塾女子高等学校など(一部、男子校・女子校の別あり)
• 明治大学付属:明治大学付属中野高等学校、中野八王子高等学校、明治大学付属明治高等学校など
• 青山学院高等部:高校受験あり
• 立教新座高等学校(埼玉県だが首都圏通学圏)
• 中央大学付属高等学校、中央大学杉並高等学校など
• 法政大学高等学校、法政大学国際高等学校など
• 日本大学系属:日本大学第一高等学校、日本大学櫻丘高等学校、日本大学豊山高等学校など
• 東洋大学附属牛込高等学校
• 専修大学附属高等学校
• 駒澤大学高等学校 など
これらの学校は、大学への内部進学制度が整っており、学校によってはほぼ100%の進学率を誇るところもあります。一方、内部進学といっても大学進学試験や評定基準など、一定のハードルが設けられている学校が大半であることにも注意が必要です。
4. 高大一貫校のメリット
1)大学までの道筋が明確になる
最大のメリットは、大学までエスカレーター式に進学できることでしょう。特に難関大学の附属高校の場合、一度合格すれば大学受験に際して一般受験よりも有利になります。附属校によっては専願制度を設けているため、在学中に必要な成績を修めることができれば、そのまま大学へ内部進学できる可能性が高いです。保護者の皆さんにとっては、大学受験の不確定要素を大幅に減らせるという安心感があります。
2)受験勉強に追われすぎず、多彩な体験ができる
大学受験を見据えた厳しい学習カリキュラムを持つ中高一貫校と異なり、高大一貫校では高校入学以降に比較的時間に余裕ができるケースも見られます。というのも、一般受験ではなく内部進学が基本となるため、最難関大学を目指すようなハードな受験対策に追われる状況が少なくなるからです。
その結果、部活動や課外活動、留学プログラム、インターンシップなどに力を入れる生徒が多く、大学生さながらの幅広い体験を積むことができます。もちろん学校や生徒の志向によって差はありますが、勉強だけでなく総合的に成長できる環境が整いやすいのが特徴です。
3)総合型選抜にチャレンジしやすい
近年注目度が上がってきている総合型選抜入試。入試による学力一発勝負ではないこの入試方式が、今後も増加していくものと思われます。
しかし、まだ新しい入試方法がゆえに、志願者も右往左往しているのが現状です。特に課外プログラムに関しては、「倍率が高く不確実性も高い総合型入試対策に割く時間がない」ということで、短期のボランティアなどに「参加するだけ」という志望者がほとんどです(もちろん、一部難関大ではとんでもない実績を引っ提げて受験する受験者もいます)。
その点、もし附属の大学以外を受験したいとなった際は、この総合型入試対策に費やす時間がとりやすいのです。
もちろん、ただ多くの時間を課外プログラムに費やせばそれで良いと言うわけではありません。学習塾ESCAでは総合型選抜の実績も豊富ですので、ぜひご相談ください。
4)難関大学の受験対策を一部免除できる
難関大学の一般入試は非常に熾烈ですが、高大一貫校の生徒は一定の条件(内部進学試験や日頃の成績など)をクリアすることで一般受験を回避できる場合があります。特に私立大学附属の場合、大学ごとに設けられた基準を満たすことで内部進学が保証されることが多いです。
これにより、大学受験において多くの費用や時間を使わずに済む可能性が高くなり、結果的に大学進学までのコストを抑えられるという利点につながります。
5. 高大一貫校のデメリット
1)大学の選択肢が狭まる
最も大きなデメリットは、大学の選択肢が事実上固定化されやすいことでしょう。もちろん、附属大学以外の受験を認めている学校も多いですが、いざ外部大学を受験しようとすると内部進学の優遇を捨てることになり、大きなリスクを伴います。そのため、「高校に合格した段階で将来の大学がほぼ決まる」ことをネガティブにとらえる生徒や保護者も少なくありません。
2)学習意欲の低下リスク
大学進学がほぼ保証されている環境では、一部の生徒が「モチベーションを失う」ケースもあります。一般受験が控えていれば常に勉強に力を入れざるを得ませんが、内部進学コースではそこまでの受験プレッシャーがありません。結果的に学習意欲が薄れてしまい、大学に入った後で苦労する可能性も指摘されています。
3)学費の高さ
大学附属校、特に私立の場合は学費が高額になりがちです。もちろん学校によって違いはあるものの、入学金や施設費、寄付金なども含めると、公立校に比べてかなり高い負担となるケースが多いです。大学まで通うことを前提とすると、総額がさらにかさむ可能性もあります。
もっとも、高大一貫校であっても一般入試対策のために高額な受験塾や予備校に通う必要が薄れるので、トータルで考えると「コストパフォーマンスが良い」と考えるご家庭もあります。
6. まとめ
東京都内をはじめ首都圏では、長らく「中学受験→中高一貫校」というルートが注目されてきました。しかし近年では、“高校受験”というタイミングを利用して高大一貫校(大学附属校)へ進学するルートを選ぶご家庭も増えています。
大学受験までの道のりを考えると、中学受験よりも費用面での負担が軽減できる場合が多く、さらに難関大学を見据えたエスカレーター方式の安心感が得られるのが魅力です。
一方で、「大学の選択肢が事実上固定される」「受験モチベーションを失いやすい」「学費自体は私立なので高め」などのデメリットがあるのも事実です。最終的には、お子様の学習意欲や将来の進路希望、経済状況などを総合的に判断して決めることが大切になります。
もし「高校から大学附属校を目指したい」「中学受験は子どもに負担が大きそうで迷う」という保護者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、学習塾ESCAにご相談ください。生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせたカリキュラムをご提案し、適切な時期からの受験対策をサポートいたします。
高大一貫校の受験に向けては中学校3年生からの準備だけでなく、中学1〜2年生の基礎固めが重要です。英語や数学など、中学校範囲の学習内容をしっかりと身につけておくことで、高校受験の際には大きなアドバンテージを得られます。早めの対策こそが合格への近道です。
学習塾ESCAでは、お子様の夢や目標に合わせた学習サポートを行っています。部活と勉強の両立や、大学進学を含めた将来的なビジョンづくりなど、総合的にバックアップいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
本記事が、高大一貫校の高校入試を検討するうえでの一助となれば幸いです。お子様の未来の選択肢を広げるためにも、東京都内の受験事情をしっかりと押さえながら、最適な進路を見つけていただければと思います。疑問や不安がありましたら、ぜひ学習塾ESCAへご相談ください。
学習塾ESCAへのお問い合わせはこちら
LINE無料相談はこちら
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする