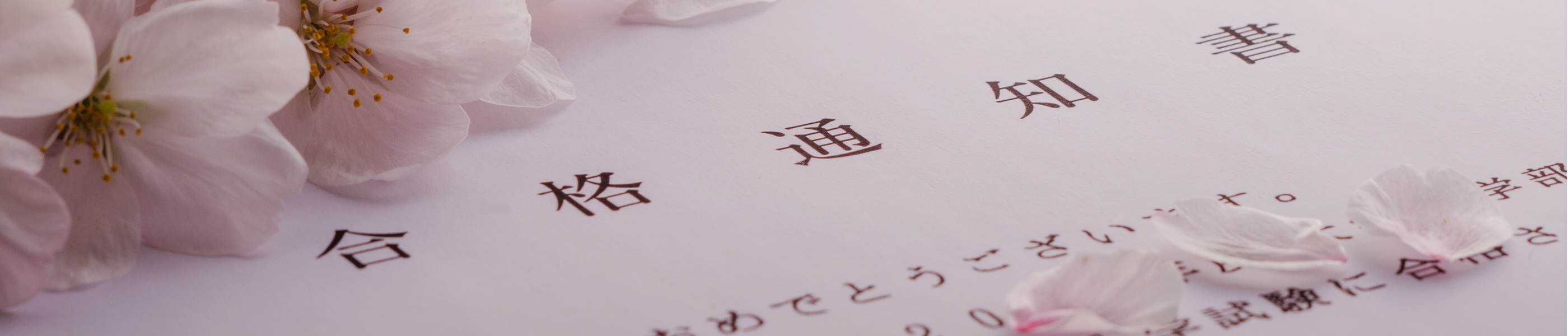Blog コラム
【総合型選抜の実態】課外プログラムは本当に評価されるのか?入試要項とデータから読み解く
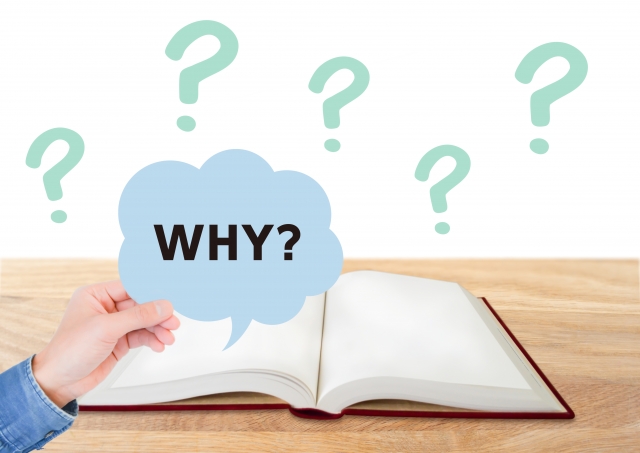
「課外活動が重要」と言われるけれど本当?
総合型選抜(旧AO入試)では、「課外活動が重要」とよく言われます。SNSや塾の広告でも「このプログラムに参加しないと不利になる」といった文言を目にする機会が増えました。実際、ESCAにも「課外活動をしていないと受かりませんか?」という相談が多く寄せられます。
しかし本当に、課外活動をしていないと総合型選抜では合格できないのでしょうか?その一方で、「課外活動なんて必要ないでしょ」という極端な意見も見かけます。
この記事では、そうした両極端な考えから離れ、実際の入試要項や講評データをもとに、課外活動の本当の位置づけを見ていきます。また、ESCAとしては課外活動を「仮説検証の場」「問いを深める機会」として有効活用してほしいと考えており、その立場からも具体的に解説していきます。
課外プログラムは「参加の意図」が重要
先日、株式会社日本進学教育研究所より以下のようなアンケート結果が公表されました。
こちらはこれまで不透明だった総合型選抜の採点基準についてアンケートを実施した非常に有意義なアンケートです。
これまでも「課外プログラムの必要性」に関しては体験格差につながるなどの世間の声もあり、採点基準に含まれているのかどうかが分かりずらかったのですが、このアンケートにより課外プログラムへの参加それ自体が重視されているわけではない、ということが明らかになりました。
では、課外プログラムには参加する必要性が全くないのでしょうか。それはそれでせっかく努力してきた生徒がかわいそうな気もします。
これはあくまで「課外プログラムへの参加」それ自体が評価されないということだと考えられます。つまり、課外プログラムにとりあえず(受動的に)参加した、という生徒を振るい落とすということです。
後の章にて詳しく解説しますが、課外プログラムというのはあくまでも主催者が「準備してくれているプログラム」です。もちろん、そのプログラムが自分の研究の目的にマッチしていれば問題ないですが、大学が求める主体的な学びという点からすると、単に用意されたプログラムに参加することに意味はないのです。
それよりも、自分の問いの仮説検証のためにどれだけ活動ができたか(文献調査、大学範囲の予習、フィールド調査など)、ということが重要になってきます。もちろん、この目的で参加する課外プログラムには価値があります。
大学の入試要項で求められる「主体性」と課外活動の関係
多くの大学の総合型選抜では、「主体性」「協働性」「社会貢献」「問題意識」といったキーワードが入試要項に明記されています。
たとえば、慶應義塾大学SFCでは「自ら課題を発見し、他者と協働して解決に取り組んだ経験」が評価対象とされています。また、上智大学総合グローバル学部では「学外活動を通じて学びを深めた経験」や「他者と協働した経験」が重視されると要項に明記されています。
これらの大学では「活動の内容」そのものというよりも、「その活動から何を学び、どのように考え、将来につなげようとしているか」に重点が置かれていることが分かります。
また、東京女子医科大学看護学部や東邦大学看護学部では、「これまでの経験を通じて得た気づきや学び」「主体的に行動した経験」の記述が求められています。
さらに、桜美林大学では「Spiral(スパイラル)」という課外プログラムを修了した生徒専用の入試を実施しています。これはまさしく、課外プログラムが出願条件となっているタイプの入試です。
一方で、多くの大学では課外活動は必須ではありません。活動の有無よりも、それを通じて得た問いや学び、構想力が評価される仕組みになっています。
つまり、大学ごとにスタンスは異なるため、「自分の志望校がどのような観点で評価するか」を理解することが最も重要なのです。
データに見る課外活動の扱い
文部科学省やベネッセ教育総合研究所などが公表している大学入試講評でも、「活動の実績よりも、思考のプロセスや学びの深さを重視する」という傾向が明らかになっています。
たとえば、ある講評では「高校時代に取り組んだ活動の中で、何を課題と捉え、どう向き合ってきたかを評価した」と記されています。また、別の講評では「活動そのものよりも、志望理由書での言語化力や将来への構想が合否を分けた」と明言されています。
また、近年の講評では「研究力」というキーワードも散見されます。研究力とは明確に定義されているわけではありませんが、ESCAではそれを「問いを立て、問題の構造を捉え、仮説を立て、検証し、考察を通じて新たな問いを生み出す力」と捉えています。つまり、単なる活動経験ではなく、それを通じた思考の深まりと構造化が問われているのです。
これらの講評は、「課外活動=加点要素」と単純に捉えるのではなく、その中でどのように思考し、問いを持ち、どのように振り返ったかが重要であることを示しています。
どんな活動が評価されやすい?実例と傾向
「どんな活動をすれば評価されますか?」という質問も多く受けますが、実際には活動の種類よりも、それを通じた気づきや構想力の方がはるかに重視されます。
たとえば、文化祭の実行委員や部活動のキャプテン、地域のボランティア活動、インターンシップなど、どれも評価対象になりますが、単に「やりました」だけでは評価されません。大切なのは、
- なぜその活動に参加したのか(背景・動機)
- 活動中にどのような問いを持ち、試行錯誤したか(仮説検証)
- その経験が今後の学びや志望理由につながっているか(構想)
です。
また、仮説検証の場は課外プログラムだけでなく、日常的な観察やインタビュー調査などでも代替可能です。重要なのは、「問いを深めた経験」があるかどうか。ESCAでは、生徒それぞれに合った形でそのプロセスをサポートしています。もちろん、オンラインでの指導でもこのプロセスを重視しています。
まとめ ― 「課外活動=必須」ではないが、「問いを深める場」として有効
結論として、「課外活動がなければ総合型選抜は通用しない」というのは誤解です。多くの大学では、活動の有無そのものではなく、そこからの思考と構想が問われています。
一方で、一部の大学(例:桜美林大学のSpiral方式や筑波大学の特別選抜など)では、特定のプログラムの修了が出願条件となるケースもあり、大学ごとの方針をよく確認することが不可欠です。
課外プログラムは、問いを深め、仮説を検証するための有効な場となり得ます。ESCAとしては、そうした場に積極的に挑戦してほしいと考えていますが、それが難しい生徒でも、探究的な姿勢や構想力は十分に養うことができます。
大切なのは、「何をしたか」ではなく、「なぜそれをしたのか」「どのように学び、考え、未来につなげているのか」。その本質を理解したうえで、大学ごとの入試方針に合わせた戦略を立てていきましょう。
学習塾ESCAへのお問い合わせはこちら
LINE無料相談はこちら
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする